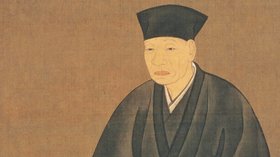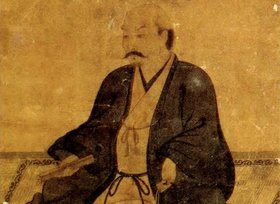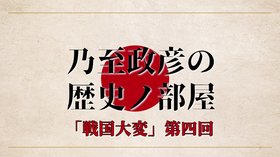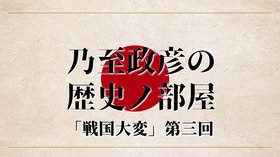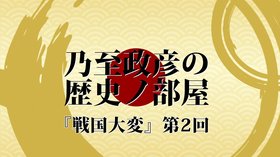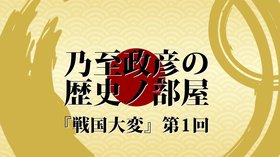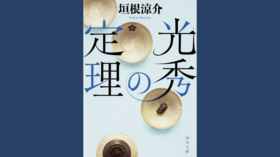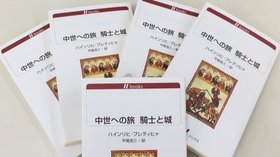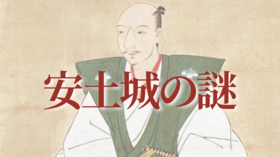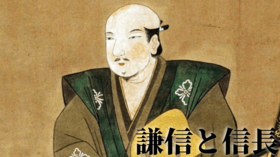常陸の不死鳥と呼ばれる戦国大名・小田氏治。
連戦連敗のデータをベースに 「戦国最弱」と呼ばれることも多く、あまり有能ではないイメージが定着しつつある。だが、本当に弱い武将が何度も大きな合戦にチャレンジできるのだろうか……?
「小田氏治の合戦」をテーマにその実像に迫りなおしていく連載。今回は前回に引き続き、「山王堂合戦」について。上杉謙信と小田氏治が永禄7年に戦ったとされる合戦の背景に隠された実相を突き止めていきます。
歴史家。著書に『戦国大変 決断を迫られた武将たち』『謙信越山』(SYNCHRONOUS BOOKS)、『上杉謙信の夢と野望』(KKベストセラーズ)、『平将門と天慶の乱』『戦国の陣形』(講談社現代新書)など。書籍監修や講演活動なども行なっている。1974年生まれ。高松市出身、相模原市在住。
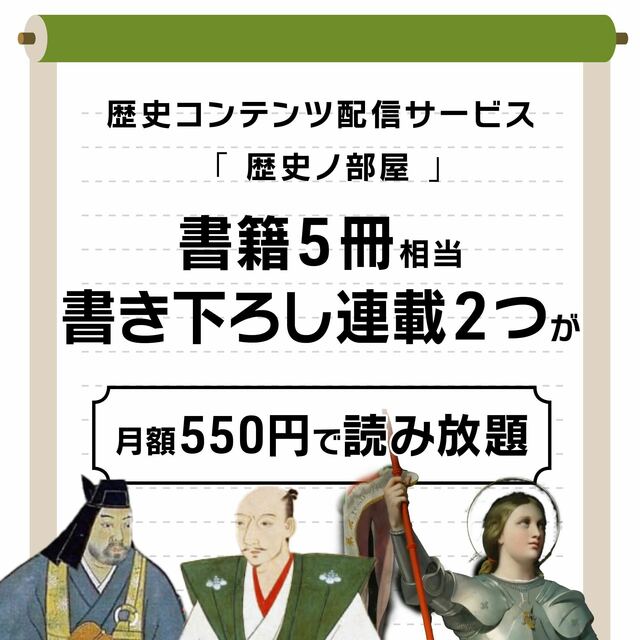
一次史料が示す永禄七年正月の土浦城合戦
ここで、小丸氏が参考にした一次史料の該当部分を見てみよう。
永禄7年8月4日に、上杉謙信(当時は輝虎)が京都の大舘晴光に宛てた書状である。
常州小田氏治事[中略]当春至于小田地馳向、彼要害旧地、殊年来普請籠手候間、可相責事大切之由、雖各被申候、取詰為攻之候故落居、宗徒者二千余討捕、残党或堀溝溺死、或焼死者、幾千万不知其数候、小田同意之地、当日三十余ヶ所、出証人降参仕候、
ここに謙信が永禄7年の「当春」に小田氏治を攻めて2000余を討ち取った記述がある。小丸氏はこれが山王堂合戦を示すものとして、軍記の合戦内容を永禄7年に移すことにしたようである。
だが、この記述には野戦をした形跡がない。
もし先の軍記2冊にある通り、氏治を激戦で撃破して、重臣の息子を討ち取り、城に追い込む大戦果を挙げたなら、そこを漏らさず書き記したはずである。
なのに謙信は、これを明記していない。
ところでほかの二次史料を見てみると、永禄7年正月に謙信が氏治の居城を攻めた記録が多数ある(『烟田旧記』『和漢合運』『謙信公御年譜』『佐竹家譜』等)。
しかも攻めたのは小田城や藤澤城ではなく、土浦城で、どれも城攻めて二千人余りを討ち取ったと記している。
先の謙信書状にある「宗徒者二千余討捕、残党或堀溝溺死、或焼死者、幾千万不知其数候」と一致する。堀の溝に落ちて溺死する者と焼死した者が無数にいたとする説明も城攻めの内容である。
この書状に書いてあるのは、4月に行なわれた上杉謙信と小田氏治の野戦ではなく、正月に行なわれた上杉謙信が小田氏治の立て籠もる土浦城を陥落させた「土浦城合戦」なのである。
つまり謙信書状は、「山王堂合戦」の実在を裏付ける証拠とはならない。
山王堂合戦が〈創作〉された理由

では、なぜ謙信と氏治が野戦をしたとする軍記が作られたのだろうか。
これには、ちょっとしたからくりがある。...