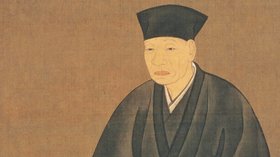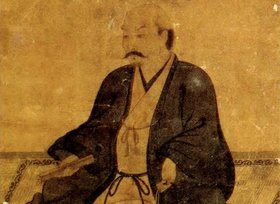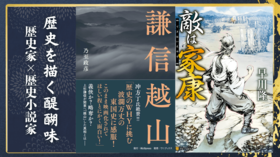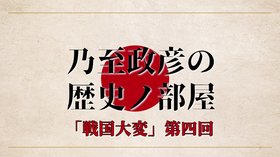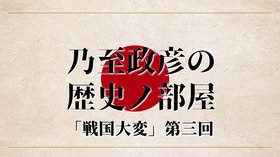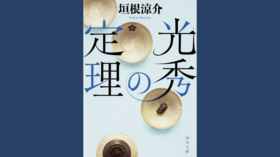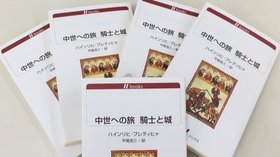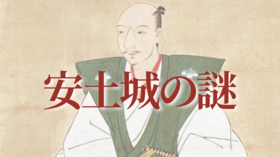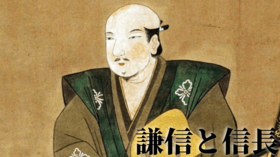「歴史ノ部屋」でしか読めない、戦国にまつわるウラ話。今回は『信長の野望』 検証記第6回。
信長の野望シリーズ2作目となる「全国版」は、日本全土の戦国大名が大勢登場することになった。地域のプレイヤーたちが自分の国を選んで互いに国盗り、天下取りを狙い合う遊び方を提供した。今見ると単純なシステムではあるが、今日の製品では採用されないような不思議なところもある。その違和感に接近して見ると、歴史シミュレーションゲーム黎明期ならではの試行錯誤の跡を読み取ることができる。
歴史家。著書に『戦国大変 決断を迫られた武将たち』『謙信越山』(SYNCHRONOUS BOOKS)、『上杉謙信の夢と野望』(KKベストセラーズ)、『平将門と天慶の乱』『戦国の陣形』(講談社現代新書)など。書籍監修や講演活動なども行なっている。1974年生まれ。高松市出身、相模原市在住。
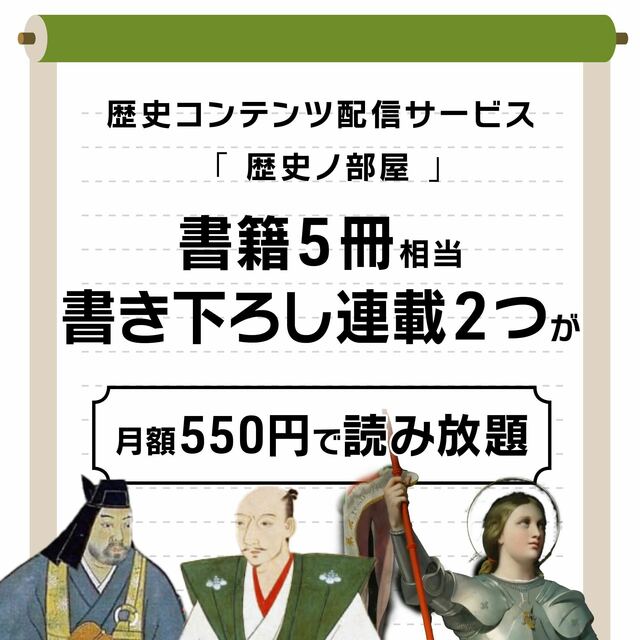
コンピュータゲームとボードゲームの分岐点
ついで3年後の1986年、『信長の野望』の「全国版」が発売された。同年には、ボードゲーム普及の名作とされる『戦国大名』(エポック社)が発売されている。
「全国版」も『戦国大名』も自勢力のマネジメントをやりながら、他勢力の妨害と攻撃を繰り返して領土を拡大して天下を取るゲームで、どこからでも天下を取れる、自分に馴染みのある「おらが国」で戦国時代に入り込める、基本は国単位でエリアを統治するなど、共通点は多かった。1人ではなく多人数で遊ぶパーティゲームの側面もあった。
『戦国大名』には、マネジメントの概念が取り入れられており初代『信長の野望』の影響があることを否定できないので、その申し子たる両者が似ているのも当然といえば当然のことである。
このように大筋では兄弟のように似通っているところがあったが、たとえ兄弟であっても成人すればそれぞれ別の人生を歩むように、『信長の野望』と『戦国大名』が向き合う市場の客層と範囲には大きな違いがあった。
必然の流れではあるが、光栄の『信長の野望』は今後拡大するであろうコンピュータゲームのユーザーを、エポック社の『戦国大名』は従来のウォーシミュレーションゲームを好む伝統的ユーザーを重視してデザインしたのである。
ボードゲームのウォーシミュレーションは、指揮官がゲームを通して戦争に勝利する机上の「作戦演習(=兵棋演習)」に源流があり、伝統的ユーザーにはリアリティを求める傾向が強い。多少システムが複雑であっても現実を体感させる仕組みであれば、歓迎された。その落とし込みの巧みさを味わうところもあった。
いっぽうコンピュータのシミュレーションゲームは、そのような伝統に触れていない客層がメインとなる。コンピュータ雑誌や店頭で『信長の野望』のタイトルを見かけた人々に「やってみようかな」と思わせるには、あくまでコンピュータゲームとしての面白みを強化する必要があった。
そこにシブサワ・コウの歴史への思いが合わさって、「全国版」は初代の舞台を全国に拡大するだけでなく、細部のデザインが見直されていた。
オリジナルの国数
登場する国の数は50。これは実際の国数より少ない。一部、薩摩(さつま)国と大隅(おおすみ)国を合体させて「薩摩大隅」という国名にしているところがあった。...